多くの男性は厚化粧より薄化粧の女性の方が好きだというデータがあるそうです。
僕もひどく共感できます。
その一方で、化粧は洋服で着飾るようなものだという女性の意見もあるそうです。
なるほど、確かにそれも理解できます。
それであるならば、人にはそれぞれに合う洋服があるのと同じように、
厚化粧が似合う人、薄化粧で映える人がいるのでしょう。
そうは思いつつも、僕は以前厚化粧な女性を見た時ある妄想をしてしまったのです。
A子は化粧台に向かっていた。バイトに向かう直前のことだった。
一人暮らしで大学生の彼女のバイト先はいわゆる風俗営業店。
もちろんそこでバイトしていることなど友達や家族に話したことなんてない。
誰にだってある人に知られたくない一面、A子にとってのそれはバイトのことであった。
普段はさほど濃いめの化粧をすることはないが、バイトに向かうときには別だった。
まるで別の人格を作っているようだとA子は思っていたが、むしろそれが楽しくもあった。
厚めに塗ったファンデーションは彼女にとってのスイッチだった。
季節は初夏を迎えていた。
今年の夏も友達とパーッと遊ぼう。A子はそう考えていた。
格別お金に余裕のある家庭に生まれ育ったわけではなかった彼女のお財布事情は、
このバイトをしていなければかなり厳しい物だった。
もうすぐ就活を控えている。みんなでバカ騒ぎできる夏はこれで最後かもしれない。
夏の間はバイトにあまり行けないことを考えると、このあたりで稼いでおかなければ。
その思いから普段よりも多めにシフトを入れていた。
そのせいだろうか、最近疲れがとれないことが多いとA子は感じていた。
昼間は大学、夜はバイト。交友関係も狭くはなかったので遊びに誘われることもよくあった。
最近化粧のノリが悪いのも無理がたたっているせいなのだろうか。
友達にも「この前のA子はなんだかいつもと雰囲気が違った」と言われたこともあった。
出勤すると、店の常連のお客さんがA子を指名した。
そのお客はいつも上機嫌で羽振りが良いので、楽で良い男だとA子は思っていたが、
指名されたのはその日が初めてだった。
「この前は俺の相談に乗ってくれてありがとう!」
A子にはその男の相談というのが何の事だかわからなかったが、どういたしましてと答えておいた。
どうせ違う人と間違えているのだろう、酔った男にはよくあることだ。
A子は男の話に微笑みながら適当に相槌を打っていたが、どうも話の辻妻が合わないことが多かった。
男は仕事のことでちょっとした悩みがあり、愚痴のようにそれをこぼしたところ、
A子が親身になって考えてくれ、そこで出た答えがとてもうまく行ったのだと嬉しそうに語っていたが、
彼女にはそのなに一つにも身に覚えがなかった。
あまりにも男が感謝してくれたのが気になり、前回はいつ来たのか聞いてみたところ、3日前だと男は言った。
3日前?その日はバイトには来ていないはずだ。
やはり男の勘違いに違いない。A子はそう思った。
ところが男が帰ったあとシフト表を確認すると、なんと出勤したことになっていた。
誰かが間違えて書きこんでしまったのだろうか?
何にせよ1日分給料が多く入るのだ。こんなラッキーなことはない。
あえてその分を指摘せずにA子はその日のバイトを終え、帰路に就く。
しかしなんだかひどく身体がだるい。今日はやたらと家が遠く感じる。
やっとのことで帰宅すると同時にA子は倒れこむようにベッドの中へもぐりこんだ。
翌日、目を覚ますと昼を過ぎていた。
しまった、午前中にも講義があったのに。
しかも朝一番だからもうすでに数回休んでしまっているはずだ。
幸いなことに仲の良い友人もその講義を受講している。
おそらく代弁してくれていると思うが、メールで確認を取っておこう。
返信が来るまでの間にA子は午後の授業に向けて急いでシャワーを浴びようと風呂場へ向かうと、
いつも髪形や化粧をチェックしている鏡が目に入った。
昨日のけだるさのためか顔がむくんでいるし、髪もボサボサだったが、化粧がきれいに落ちていた。
おかしい、私は昨日化粧を落としてから寝ただろうか?
あまりに疲れていたため記憶があいまいだ。
しかし今はとにかく午後の授業に備えなければ。
シャワーを浴び終え携帯電話に目をやると、メールが来たことを知らせるランプが点滅していた。
メールはやはり友人からのものであったが、その文面をA子は理解できなかった。
「何言ってるの?ちゃんと出席してたじゃない。」
彼女は一体何を言っているのだろう?
私はついさっきまでここで眠っていたはずだ。
見間違いじゃないのかとメールを送ると、返事はすぐにやってきた。
「私の隣に座ってたじゃない。忘れ物したとかで帰ったばかりでしょ?」
何の事だかさっぱりわからない。からかわれているのだろうか?
それはそうとあまり時間がない。ささっと身支度を整えなければ。
洋服を見繕い、髪をおざなりに乾かしたのちに整え、化粧台の前へ。
肌の調子は悪そうで、きちんとするには時間がかかってしまうだろうが、
ここは厚化粧になってしまってでも素早く整えなくてはならない。
しかし、焦りながらメイクをすればするほど化粧が乗らない。
どういうことだろう、ファンデーションもアイラインもチークも口紅も、
何もかもが肌の上にある気がしない。まるですっぴんのようだった。
時計に目をやると、時間に余裕がほとんどない。
不気味な現象に戸惑うA子がもう一度鏡をみると、
そこにはばっちりと化粧を施した彼女の顔が映し出され、口が勝手に動いていた。
「ありがとう。きれいになったよ。」


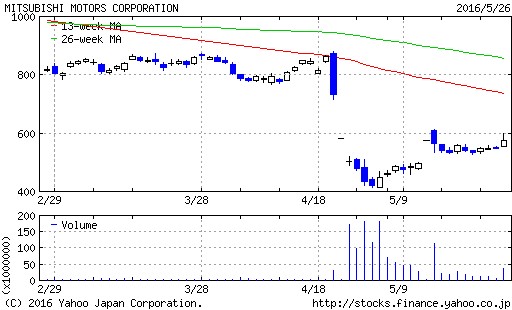

コメント